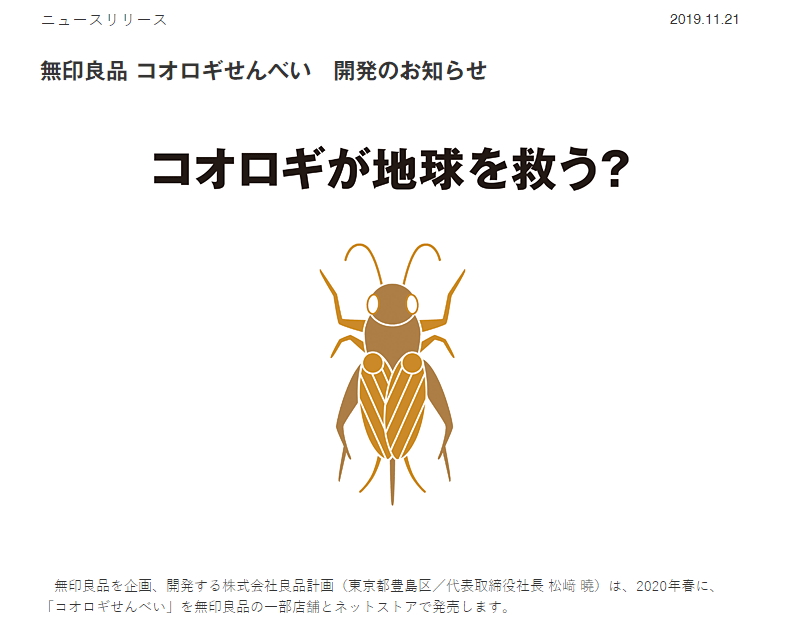女優のニコール・キッドマンさんが昆虫を食べる様子が話題となりました。
Nicole Kidman Eats Bugs | Secret Talent Theatre | Vanity Fair
「世界で20億人が虫を食べるの。私もその中の一人よ!」と言いながら、タバコイモムシやゴミムシダマシを生きたまま食べたり、コオロギやバッタを美味しそうに食べたりしています。ゴキブリやクモもいけちゃうそうです。
優雅に虫を食べる姿は、とても絵になりますね。まるで、一般人には想像もつかない未来を先取りしているかのようです。
FAO の取り組み & 昆虫食のメリット
FAO(食糧農業機関)は、2003年から、多くの国々で食用昆虫というテーマに取り組んでいます(FAO - Insects for food and feed)。
また、2013年に出した報告書(The State of Food and Agriculture 2013)では、世界の人口があと 30年ほどで 90億人に達し、食料不足が深刻化するため、栄養価の高い昆虫に注目すべきことを発表しています。
現在、食料(たんぱく源)の代表といえば家畜ですが、家畜の飼育には大量の穀物を必要とするため、かなり飼育効率が悪いのです。
たとえば、飼育に必要な穀物の量は、牛肉1kgに 10~20kg、豚肉1kgに 5~10kg、鶏肉1kgに5kg前後と言われています。しかも、家畜は、地球温暖化の原因物質として悪名高いメタンガスを大量に発生します(全体の1/3が家畜からという報告も)。
これに対して、昆虫は、飼育に必要な穀物がかなり少なくて済みます。たとえば、1kgのコオロギは、その倍の2kg程度の穀物で飼育できるそうです。
日本の昆虫食の現状(ビジネス・研究・投資)
日本国内でも、昆虫を使った調味料や昆虫食通販・レストラン、食用昆虫の研究やビジネスなどが一部で盛り上がりを見せています。
イナゴソース
「いなか伝承社」という地域団体では、醤油の伝統技術を利用した「イナゴソース」を開発・販売していますね。
これは、醤油発祥の地の一つである和歌山県湯浅町の「昔ながらの醤油の技術がまだ残っているコト」を地域資源と捉えて、そこに「いなか」のイメージを形成する要素であり、未利用資源でもある「昆虫」(今回はイナゴ)を組み合わせて、湯浅町の100年以上の伝統ある醤油醸造元「湯浅醤油」様に技術協力頂いて、本格的な、全く新しい発酵調味料に挑戦いたしました。
昆虫食通販
昆虫食通販ショップの「TAKEO」さんでは、昆虫のスナック、昆虫のおかし、昆虫のパスタ、昆虫の粉などなど、いろんな昆虫商品が販売されています。
売れ筋は、サソリ、タガメ、カブトムシ、コガネムシ、タランチュラなどだそうです。
食用昆虫の研究
「NPO法人 食用昆虫科学研究会」では、「科学的な取り組みを通じて昆虫と人との関わりを支援し、食利用を中心とする昆虫の新しい社会的役割を提案する」ことを理念として、さまざまな昆虫食情報を提供しています。
旧サイトには、「虫の味」というページもあり、バッタ類、カメムシ類、セミ類、チョウ・ガ類、甲虫(カブトムシ、カミキリ)類、トンボ類、ハチ・アリ類、クモ類などなど、いろんな虫の食べ方、味わいが紹介されており、とても面白いですね(虫が苦手な方は要注意)。
養魚飼料用コオロギの開発
人間が排出する野菜クズで育てたコオロギを魚のエサとして与え、その魚を人間が食べるというエコシステムを実現しようという「Ecologgie(エコロギー)」プロジェクトも面白いですね。「エコロジー」と「コオロギ」に由来する命名です。養殖の飼料コストを抑えられますし、生ごみも減らせます。
このビジネスが成功し、コオロギで育った魚がスーパーやお寿司屋さんに登場するようになれば、水産業関係では、近畿大学の「養殖マグロ」以来の大きな話題となるかもしれません。
無印良品「コオロギせんべい」
2019年11月、(株)良品計画は、徳島大学との連携により、コオロギの粉末をせんべいに練り込んだ商品を発売すると発表しました。そして、2020年の春から実際に売り出されています。栄養価が高く、環境負荷が少なく、とりわけ食用に適したコオロギの特性を活かして、今後訪れるであろう「昆虫食」社会をリードする新しい取り組みです。
昆虫食レストラン「アントシカダ」
2020年6月、コロナ禍の東京でオープンしたのが、昆虫食レストラン「アントシカダ(ANTCICADA)」です。この名称は、「アリとキリギリス」の元のタイトル「アリとセミ」に由来し、さまざまな虫の個性を引き出そうとする思いが詰まっているそうです。
魅力ある食材の1つとして昆虫食の普及に寄与しつつ、「食とは何か?」という本質的なテーマを掲げています。日本の昆虫食をリードする存在となるでしょう。
21世紀|昆虫食の未来予想
今、格差社会と言われています。
今後、新興国や途上国がもっと発展すれば、必然的に、国際的な格差が国内的な格差へと移行してゆくのでしょう。その上、世界的な人口の爆発ですから、穀物の争奪戦が予想され、それに続いて以下のような流れが想定されます。
⇒ 穀物の価格が上がれば、肉類の価格も上がる。
⇒ 肉類へと移行しがちな先進国の食事は、再び魚類中心に戻る。
⇒ 今度は水産資源が枯渇して、魚類の価格も上がる。
⇒ 先進国の一部でも昆虫食の導入が必要になってくる。

もう1つの流れとして、昆虫から、さらに小型の生物への移行が考えられます。
生物というのは、サイズが大きいほど、成長(飼育)に必要な重量当たりのエネルギーが多くなる傾向にあり、とにかく効率が悪いです。
最近、ミドリムシ(ユーグレナ)が栄養補助食品や機能性食品として注目されているように、地球環境保護の観点からは、より小型で効率的かつ栄養価の高い食料の開発が進むことになるものと思われます(ご存知の通り、ミドリムシは「虫」ではなく、「藻」の一種ですね)。
短期的には農業や畜産業の重要性が高まりますが、その先には、昆虫食の分野も重要性が高まり、投資分野としても非常に注目されます。
昆虫食の課題
今後の食糧問題を解決する持続可能な食糧源として注目されている昆虫食(食用昆虫)ですが、もちろん課題もあります。
- 昆虫の乱獲
- 大量の昆虫の養殖が環境に及ぼす影響
- 昆虫の餌(穀物や小動物)の確保
- 大量生産や保存・輸送のための製造・加工技術の確立
今後は、こういった課題に道筋をつけながら、少しずつ昆虫食が社会に浸透していくことになるのかもしれません。
まとめ
テレビなどでは、相変わらず昆虫食がゲテモノ扱いされていますが、そろそろ新しい取り組みとして、昆虫料理の3分クッキングなんてどうでしょうね。
日ごろから慣れ親しんでおけば、今の子どもが大きくなるころには、無理なく昆虫食に移行できるのではないでしょうか。
昆虫食の歴史や栄養学、未来の可能性が学べます。「セミの天ぷら」「イナゴのかき揚げ」「タガメうどん」「ミールワームチャーハン」などのレシピも豊富です。